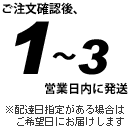2009年5月20日、RCCラジオ「桑原しおりの基町こまち」内コーナー「こまちセレクション」にて、放送された「ふくやま鯛茶漬け」のレシピを公開します。
ふくやま鯛茶漬けプロジェクト 〜 郷土料理うずみと新しい食文化の提案

ふくやま鯛茶漬け(アジア風)
ナンプラーとごま油で漬けた鯛、野菜のナムルをのせたアジア風のお茶漬けです。ごま油の風味が食欲をそそります。
材料(4人分)
| 鯛の薄切り | 8枚 | |
| 水 | 500cc | |
| ごま油 | 少々 | |
| ごはん | 300g | |
| 糸唐辛子 | 少々 | |
| A | ナンプラー | 大さじ 1/2 |
| ごま油 | 小さじ 1/2 | |
| 小松菜 | 1/2束 | |
| もやし(太め) | 1/2袋 | |
| B | こいくち醤油 | 小さじ 1 |
| ごま油 | 少々 | |
| 砂糖 | 小さじ 1/3 | |
| すり白ごま | 大さじ 1 | |
| すり生姜 | 少々 | |
| C | 中華スープの素(ウエイパー) | 8g |

作り方
(1) 鯛の切り身は[A]に漬け冷蔵庫に10〜15分入れておく。
(2) 小松菜は3cmの長さに切り、もやしと一緒に茹でて冷水に取る。水気を切って[B]と和える。
(3) 鍋に[C]を入れて沸騰したら、ごま油を加えて火を止める。
(4) お茶碗に、ご飯と(2)を入れて、鯛の切り身をバラの花びらのように盛り付ける。(3)をかけて、糸唐辛子をのせる。
※ ナンプラー(タイ料理に使われる魚介類から作られたお醤油状のもの)が無ければ、お醤油で代用できます。
ふくやま鯛茶漬け(洋風)
鯛をオリーブ油と醤油・にんにくで漬け、温かいミルクに昆布茶と白味噌を加えた、リゾットのようなお茶漬けです。
材料(4人分)
| 鯛の薄切り | 8枚 | |
| アスパラ | 2本 | |
| 枝豆(冷凍さやつき) | 60g | |
| パプリカ 赤・黄 | 各1/4個 | |
| アーモンド | 8粒 | |
| 粉チーズ | 適量 | |
| ご飯 | 300g | |
| ピザ用チーズ | 40g | |
| A | こいくち醤油 | 大さじ 1 |
| オリーブ油 | 大さじ 1/2 | |
| すりおろしにんにく | 少々 | |
| B | 牛乳 | 500cc |
| 昆布茶 | 小さじ 1/2 | |
| 白味噌 | 小さじ 2 |

作り方
(1) 鯛の切り身は[A]に漬けて冷蔵庫に10〜15分入れておく。
(2) アスパラは、5mmに斜め切りして、茹でる。枝豆は、さやから出す。パプリカは、1cm角にして、アーモンドは粗く刻む。
(3) 鍋に[B]を入れてかき混ぜて、温める(沸騰させないこと!)。
(4) 温かいご飯にピザ用チーズを混ぜ、お茶碗に入れる。(2)を彩りよくのせて、鯛の切り身をバラの花びらの様にのせ、まわりに粉チーズをかけて、(3)を注ぐ。
※ 牛乳にお味噌はよく合います。特に白味噌は甘味があり、まろやかな味にしてくれます。
ふくやま鯛茶漬け(和風)
すり胡麻、醤油、みりんを絡めた鯛を、焼きおにぎりにのせ、かつおだしをかけた和風のお茶漬けです。
材料(4人分)
| 鯛の薄切り | 8枚 | |
| ご飯 | 300g | |
| 具は昆布(梅干、チーズなど) | 適量 | |
| 出し汁 | 500cc | |
| A | こいくち醤油 | 大さじ 1 |
| 本みりん | 大さじ 1 | |
| レモン汁 | 小さじ 1/2 | |
| B | こいくち醤油 | 大さじ 1 |
| 蜂蜜 | 大さじ 1 |

作り方
(1) 鯛の切り身は[A]に漬け、冷蔵庫に10〜15分ぐらい漬ける。
(2) 具(昆布など)を入れたおにぎりを4個作る。フライパンにオーブンシートを敷いて、おにぎりの両面を少し(きつね色に)焼く。[B]をハケなどでぬり、再度こんがりと焼く。
(3) 器に(2)の焼きおにぎりを入れ、鯛の切り身をバラの花びらの様にのせ、その上から、だし汁をかける。お好みでわさびを添える。
※ お好みでわさびを添えても美味しいです。
「郷土料理と新しい食文化の提案」出前講座
備後特産品研究会では「郷土料理と新しい食文化の提案」という題目にて、2008年11月より福山市内の各所公民館と連携して、講義と調理実習による出前講座を行っております。
本講座では、福山の郷土料理である「うずみ」についての講義、福山の食文化についての講義とともに、「うずみ」の調理実習および鞆の浦のイメージシンボルでもある鯛を使った「鯛茶漬け」の調理実習を中心に展開します。
本出前講座の講師につきまして、備後特産品研究会・会長である中島基晴と、料理愛好家の「くどせかずえ」さんが担当させていただきます。福山市在住のくどせさんは、福山市内に配布されるフリーペーパーのレシピコーナーを担当したり、全国規模のレシピコンテストにて相次いで入賞を果たすなど様々な実績がある方で、当会の支部「福山特産品研究会」の「鯛茶漬けプロジェクト」での鯛茶漬け制作にも関わってくださっています。
備後特産品研究会による鯛茶漬けの出前講座日程表
| 日付 | 場所 / 人数 / 問合せ先 | 時間 | レシピ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年11月19日(水) ※ 報告はブログで |
引野公民館 / 16名 084-941-6665 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ お米1升を用意しています ※ 本講座は終了しました。 |
| 2008年11月20日(木) ※ 報告はブログで |
深津コミュニティーセンター / 20名 084-923-8103 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2008年11月27日(水) ※ 報告はブログで |
今津公民館 / 22名 084-934-2205 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 9:30 参加者集合 ※ 本講座は終了しました。 |
| 2008年11月28日(木) ※ 報告はブログで |
水呑公民館 084-956-3943 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2008年12月9日(火) ※ 報告はブログで |
有磨公民館 / 21名 084-958-3849 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2008年12月17日(水) ※ 報告はブログで |
緑丘公民館 / 20名 084-943-5495 |
9:30〜12:30 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年1月28日(水) ※ 報告はブログで |
春日公民館 084-947-4491 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年1月30日(金) | 赤坂公民館 084-951-1001 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年2月7日(土) ※ 報告はブログで |
山手公民館 / 15名 084-951-9381 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年2月12日(木) ※ 報告はブログで |
新涯公民館 / 17名 084-953-5634 |
10:00〜13:00 | アジアン風鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年2月25日(水) | 千田公民館 084-955-0023 |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年3月4日(水) ※ 報告はブログで |
松永公民館 - |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
| 2009年3月7日(土) | 東部ブロック社会教育センター 084-940-2574 |
10:00〜13:00 | - | 2009年3月実施の「東部文化フェスタ」の一環として、開催。 ※ 本講座は終了しました。 |
| 13:00〜16:00 | - | |||
| 2009年3月8日(日) ※ 報告はブログで |
東部ブロック社会教育センター | 10:00〜13:00 | - | |
| 13:00〜16:00 | - | |||
| 2009年3月17日(火) ※ 報告はブログで |
松永公民館 - |
10:00〜13:00 | 3色焼きおにぎり鯛茶漬け | ※ 本講座は終了しました。 |
福山の郷土料理「うずみ」について

「うずみ」とは?
江戸期の倹約政治の中、ぜいたく品とされた鶏肉・えびなどを堂々と口にすることの出来ない庶民が、具をご飯で隠しながら食べていたのが始まりと伝えられています。うずみの作り方は非常に簡単で、小エビ、椎茸、里芋、人参などの具にだし汁をかけ、その上からご飯を具材を隠すように盛ります。
「食」を通した福山地域ブランド (福山市立女子短期大学・2008年度公開講座)
※ 2009年現在、本講座はすべて終了しています。
同講座の趣旨・狙い
現在,地域の活性化,アイデンティティ(独自性)の確立といった視点から「地域ブランド」が注目されています。福山においては,歴史的資産,独自の農水産物,適度な人口などの集積があるにもかかわらず,全国的な知名度は,極めて低いと言わざるをえません。 この講座では,福山の「食」の可能性に注目し,地域の食材,その加工法,そしてブランドとしての発信という一連の流れを,いわば「社会実験」として位置づけ,講義のみならず,実習を通して市民に開かれた講座を目指します。
| 講師 | 開催日時・講座名 | 内容 |
 |
第1回('08/05/14) 「食と地域とデザイン」 佐藤俊郎(福山市立女子短期大学講師) |
食を通した福山のブランドを考えるにあたり、大きな視点からの取り組みを提案する。つまり、福山が「街」としてブランド化できるか、あるいはブランドに耐えうる中身をもった都市として認知されていくか?この視点がなければ、一過性の単発のプロジェクトに終わってしまう。継続性と市民への広がりは、ひいては福山にブランドを醸成する土壌があるかにかかっている。 |
 |
第2回('08/05/28) 「地域ブランドをクリエイトする」 小林正和(福山大学准教授) |
地域ブランドとは、地域発の商品・サービスのブランド化と地域イメージのブランド化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図るものである。そのためには市場の視点、消費者の視点、地域や住民の視点から見ることが重要で、ブランドの構築、活用、管理の3つの戦略と組織マネジメントが必要になってくる。 ここでケースとして岡山県笠岡市の「かさおかブランド」について行政主導の取り組み内容を報告した。平成18年より、「かさおかブランド」を立ち上げるため市内の地域資源・観光資源を策定し、その後平成20年1月から笠岡ブランド認定検討委員会で戦略の方向性、認定基準等を策定した。短期の認定事業と長期にわたる育成事業の2本立てで実施し、今後一過性で終わるのではなく地域住民を巻き込んだ息の長い取り組みが必要である。 |
 |
同・第2回('08/05/28) 「地域ブランドをクリエイトする」 渡辺幸三(福山市産業支援コーディネーター) |
第2回公開講座では、備後の地域コーディネーターとして精力的な活動をこなす「セイムファクトリ」渡辺幸三代表より地域ブランドと本プロジェクトの関連性についてご講義いただきました。 本講演終了後には、聴講された方々より様々な建設的意見が飛び交い、本プロジェクトスタッフにとっても非常に有意義な時間となりました。 |
 |
第3回('08/06/11) 「福山の食と地域」 山本幸一(日本料理「川長」社長) |
第3回公開講座では「日本料理川長」山本幸一代表取締役より福山の食の昔と今にまつわる貴重なお話を拝聴させていただきました。 受講者からは郷土料理にまつわる興味深い質問が活発に行われ、山本社長も一つ一つの質問に丁寧に応えてくださる、たいへん盛り上がった講義でした。 |
 |
同・第3回('08/06/11) 「福山の食と地域」 中島基晴(備後特産品研究会会長) |
第3回公開講座(2008年6月11日開催)では、日本料理 川長・山本社長の講演とともに備後特産品研究会会長・中島基晴氏にも講演いただきました。 本講演では、中島会長および同研究会が近年取り組む「備後の地域資源としての保命酒を活用した地域活性化・PR」を題材にお話しいただきました。 |
 |
第4回('08/06/25) 「素材を極める」 岡本良知(保命酒「岡本亀太郎本店」専務) |
第4回公開講座(2008年6月25日開催)では、株式会社岡本亀太郎本店(福山市鞆町)の岡本良知氏に講演いただきました。 当講演では、350余年の伝統を誇る鞆の浦の名産「保命酒」の起源から現在にいたるまでの話を、保命酒醸造老舗蔵元としての視点から語っていただきました。 備後地方の伝統ある特産品について深く学べる、貴重な講座となりました。 保命酒とは?広島県福山市鞆町(鞆の浦)名産の薬味酒。現代では鞆の浦に4社ある保命酒蔵元の中、岡本亀太郎本店の保命酒は、秘伝の16種ハーブを配合し漬け込んだお酒です。 |
 |
同・第4回('08/06/25) 「素材を極める」 金光康一(「金光味噌」専務) |
第4回公開講座(2008年6月25日開催)では、広島県府中市の名産「府中味噌」製造を手掛ける金光味噌株式会社(広島県府中市)・金光康一氏に講演いただきました。 この日、同じく講演していただいた岡本氏の「保命酒」同様、備後の特産として古くから多くのお客様に親しまれる府中味噌の製造秘話や近年の取り組み・海外展開について、丁寧に解説してくださいました。 府中味噌とは?山陽道・出雲道の要衡地、広島県府中市名産の白味噌。江戸時代中期の豪商により全国へ名を馳せた府中味噌は、古くは諸国諸大名に愛され、その後一般の人々にも親しまれ現代へと伝承されています。 |
 |
第5回('08/07/09) 「郷土の食材を味わう(調理)」 占部秀雄(福山調理研究会会長) |
第5回公開講座(2008年7月9日開催)では、「郷土の食材を味わう」というテーマの元、福山調理研究会・占部秀雄氏の指導による調理実習を行いました。 |
 |
第6回('08/07/23) 「鯛茶漬けの可能性を探る(調理)」 久戸瀬一枝(料理愛好家) |
第6回公開講座(2008年7月23日開催)では、「鯛茶漬けの可能性を探る」と題し、福山・鞆の浦をイメージする食材・鯛(たい)を使った、福山市在住の料理愛好家・久戸瀬一枝さんの指導による調理実習を行いました。 |
 |
第7回('08/08/06) 「鯛茶漬け応援アイテムとしての絣エプロン」 武井晶代(キャリアコンサルタント オフィスエミール代表) |
第7回公開講座(2008年8月6日開催)では、「キャリアコンサルタント オフィスエミール」代表の武井晶代さんにご講演いただきました。 |
 |
同・第7回('08/08/06) 「地域ブランド・プロジェクトの行方」 正保正惠(福山市立女子短期大学准教授) |
第7回公開講座(2008年8月6日開催)では、福山市立女子短期大学准教授の正保正惠先生に講演いただきました。 |